|
「例幣使」とは、朝廷がつかわした、伊勢神宮の神前に捧げ物をもっていく使者のことである。江戸時代朝廷は、徳川家康の法要のため日光東照宮にも同じように勅使を派遣した。恒例となったこの派遣のため、京から中山道を通り、倉賀野宿より日光に至るまでの道を整備した。復路は日光道から江戸に入り、東海道を使って帰京した。春の東照宮例祭に合わせ、勅使が通る道のことを「日光例幣使道」とよんだ。
伊勢崎を通るかつての例幣使道は、現在の市南部を通る国道354号と多くの部分で重なっていて、市内には現在でも、往時を偲ばせる名所が点在している。
なお、例幣使は京を4月1日に出発、15日に日光に到着した。1647年から1867年の221年間、一度も中断することがなかった。 |
 |
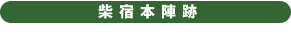 |
| 柴町524 |
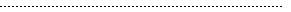 |
| 柴宿本陣は、倉賀野から日光に向かう13宿の中で、第3番目の宿場。玉村宿で一泊した例幣使一行が利根川を渡り、ここで休憩した。当時を偲ばせる黒松と門が再生された石積みの水路の脇に立っている。 |
| |
 |
|
 |
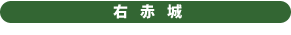 |
| 例幣使道は左手に赤城山を見ながら、西から東に進む。柴宿を発ち、馬見塚を通って、下蓮の手前、豊東橋の南詰め付近で右に曲がり、山を背にしながら南に向かう途中で、道の向きが少し西に変わる。この場所からは、ずっと左手に見えていた赤城山が右手に見える。ここが、街道の名所。 |
| |
| |
|
 |
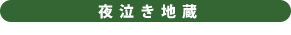 |
| 例幣使道沿いには、多くの伝説、言い伝えがある。そのひとつ、戸谷塚町の観音寺境内には、「夜泣き地蔵」といわれる天明の浅間大噴火の供養塔が建っている。泣きぐせのある赤ちゃんに地蔵がしている赤いおかけをかけてやると泣きぐせが直るという言い伝えがある。 |
| |
| |
|
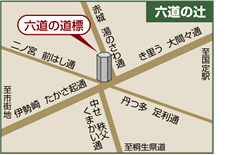 |
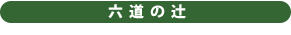 |
| 上田町249 |
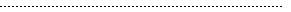 |
| 県道香林、西国定、伊勢崎線沿いにかかる上田町は、江戸時代、交通の重要な要所であったため、幕府直轄の天領となっていた。道標は六方向の道が交差している辻に、二基建てられた。旅人たちが迷わぬようにと、かのえ供養、観音供養の信仰を兼ねて造られた。当時の道標は、現在地より6m南の道中央にあった。 |
| |
 |
|
|